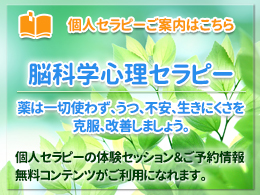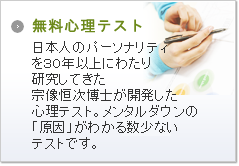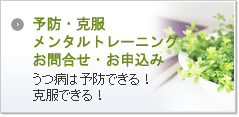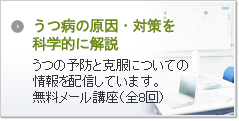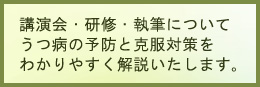企業メンタルご担当者様向け情報「本人の扁桃体の感受性が敏感すぎる課題をしっかり自覚させると、メンタル不調解決は良い結果が出せる」
弊社がご提供している、脳科学メンタルトレーニングは、慢性ストレス感情を作り出す脳内の情動の座である、扁桃体(へんとうたい)の慢性的な興奮を鎮めるというイメージワーク法を行うことで、メンタル不調を改善するということを行っております。
結論から言うと、だいたい1回2時間程度のセッションを6回~10回程度受けていただくと、メンタル不調は解決します。
なぜ、そう言い切れるかというと、弊社には現在休職中の方が個人的に費用を払って申し込んでくる方がたくさん来ますが、こういう方々が復職しているからです。
基本的にメンタルの問題とは、本人の周りの目を気にしすぎる感受性が敏感すぎる問題で、扁桃体を安定させればきれば良い結果が出ています。
扁桃体がメンタルの原因であるということは、弊社顧問の筑波大学名誉教授・宗像恒次博士が言っているだけでなく、知っている医療関係者であれば知っている事ではないかと思います。
たとえば、いま私の手元には、「月刊 臨床神経科学 2014年6月号」という月刊誌があります。
この2014年6月号は、1冊丸ごと「扁桃体」の特集を行っています。この雑誌は、医療関係者や研究者が投稿している雑誌です。
この693ページ目には「うつ病における扁桃体」という記事が掲載されていますが、これを書いているのは、国立精神・神経医療センター神経研究所の、功刀 浩(くぬぎ ひろし)さんというお医者さんです。
この方は、2013年10月20回NHKスペシャルで放映された「病の起源 うつ病」の番組にも登場した方で、扁桃体についてコメントした方です。
この原稿には次のように書かれています。
「ストレスに対するホルモン反応は視床下部を起点とするが、扁桃体が当該状況をストレスと感じると視床下部にその情報を伝え、それによってストレス応答が活性化することから、扁桃体がうつ病発症においてきわめて重要な役割を果たす」
つまり、うつには扁桃体が関係しています、ということです。
お医者さんは薬物療法で扁桃体興奮を鎮めようとすると思いますが、弊社は、心理療法で扁桃体興奮を鎮めて、メンタル改善を図っているのです。
先ほど書きましたように、個人で申し込んで来る場合、非常に良い結果が出ています。また、某上場企業では2004年から2007年まで、うつで休職の方の再発が0%という結果に貢献しました。
良い結果が出る時の条件とは何かということですが、これは次のように考えています。それは、受けにくる方が「本人自身の感受性の問題を解決する必要性がある」ときちんと認識して受けているかどうか、という点です。
再発0%に貢献した某上場企業の場合、産業保健スタッフの方々と連携して行ったのですが、この産業保健スタッフの方々と一致していたのは、メンタルの問題は本人側の心の課題があり、その課題をしっかりクリアしないと戻しません、という立場をとっていたからです。
多くの企業の場合、眠れるようになったとか、朝起きれるようになったとか、図書館に行けるようになったとか、そういうことを一つのメンタル安定の目安にするとことがあるかもしれませんが、私たちではそれだけではなく、本人側の心理課題を本人がしっかり自覚し、繰り返さないための対策をきちんと学べているかかどうかを重要視しているのです。
扁桃体興奮が安定化さsる対策をとっていないと、また同じ職場に戻ったり、同じ職場でなくても似たような人がいる部署で、また同じような刺激を受けてメンタルが不安定化するのです。
この企業では産業医が、通常のメンタル対策の場合、初回うつで休職した人の再発率は50%、2回目は70%、3回目は90%と発表しておりましたので、「本人側の心理課題をしっかり自覚させ、クリアさせる」とうことを重要視していたのです。
よって、このことをしっかりと共有でき、本人にも一緒になって啓蒙し、自分自身の課題をクリアさせる、という意識を持たせることに成功した場合、非常に好結果を生むことができます。
一方、こういう前提なしに、ただ単に「カウンセラーに面接してもらってきて」と言うだけでは、本人は自分には何も問題はないと思っていますから、そうするとメンタルトレーニングはうまくいかないわけです。
そして企業から送られてくる人は、こういう人が多いのです。これでは本人はかわいそうだと思います。自分の問題を自覚を促されることなくことなしに、ただ薬を飲み、休職するだけでは、いずれ退職を迫られる可能性大と思います。
一定の企業にとっては、やめてくれればこれにこしたことはない、という考え方をする企業もあるので、そうすると本質的な解決策は行われないですね。
一方、個人で受けにくる人は、自分の課題をクリアしようと思ってくるわけですから皆、復職し良い結果が出るわけです。
現在多くの企業の行われているメンタル対策は、自分自身に課題はあるという立場をとるものはあまり多くなく、そのことが結果的に本人に自覚を促さないために根本解決を難しくさせていると弊社では考えています。
薬を飲んだりすることは大事な面もありますがそれだけでは、本人側の課題を心理課題をクリアさせるものではないため、どこかで先ほどの再発0%の企業のような仕組みを作ることが、企業の中でのメンタル対策を成功させるポイントではないかと思います。
現在義務化されたストレスチェック制度も、職場環境要因を改善するという外部要因だけに焦点が当たっていますので、メンタル対策上、これだけではあまり効果を出すには難しいのではないかと考えています。
話をまとめますと、本人側の課題とは、本人の敏感すぎる扁桃体の感受性の課題を解決する、ということです。
こういう仕組みつくりを行うには、会社側が医療任せにするのではなく、しっかりとメンタルに対する考え方についてリーダーシップをとれることが重要です。
先の再発0%企業では、医療側と私たち心理側が同じ視点で動いていました。これは人事部側、つまり会社側がそういう視点で、私たちメンタルチームをリードするリーダーシップ力を発揮していたという点が大きいと思います。
本人に、自分自身の課題を帰結することが、結果的にメンタルを根本から解決することになる、という考え方を本人に持ってもらうよう、関係者全身で働きかけること仕組み作ること。
これがメンタル対策成功のゴールと考えています。
厚労省のメンタルへルスHP「こころの耳」では数ある心理療法の中で、唯一”メンタルヘルスカウンセリングを行うカウンセリング”と紹介しされているものです。個人カウンセリング、ラインケア、セルフケア教育、またはヘルスカウンセラー育成教育、に関心持っていただける方は、以下からお問い合わせください。既存のメンタル対策と組み合わせ、再発0%の上場企業のような結果をあなたの会社で出すことは可能です。
2016/03/23
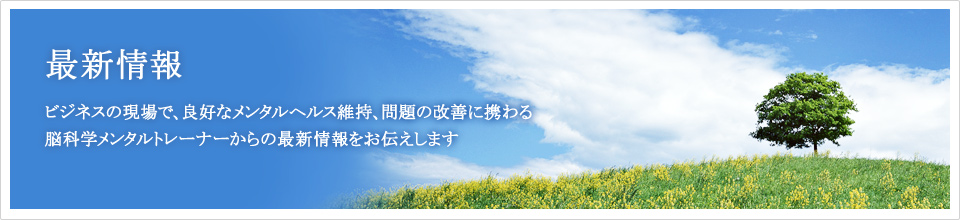
 前へ
前へ