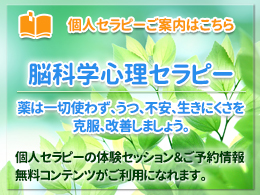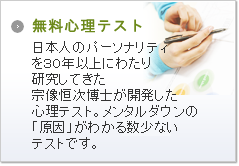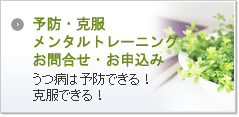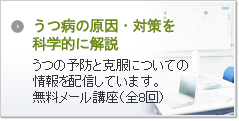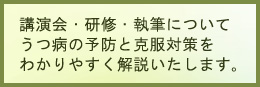メンタルヘルスの分野に、もっと「最先端科学」を!
新年あけましておめでとうございます。
いよいよ新しい年が始まりました。リーマンショック以降、沈滞し
ていた経済はまだ回復途中ですが、2014年は皆様にとってどのよう
な年になりそうでしょうか。
弊社、日本メンタル再生研究所としての今年は、今まで以上に
メンタルヘルスの世界に「科学的に効果を検証された対策」を取
り入れていく事を皆様にご提案していく年になるだろうと思って
おります。
今までのメンタルヘルス不調に対する対策は、大きく3つあった
と思います。一つ目は、産業カウンセリングが行うメンタル対策の
分野です。
これは主に「傾聴・共感」を主体とするメンタルヘルス対策だと
思います。「傾聴・共感」は非常に大切です。2つ目は、認知行動
療法が行っている分野です。その人の「考え方のクセ」が、その人
の認知を決め、それがメンタル不調を作っているのでそのクセを見
抜き改善していこうとするものです。「考え方のクセ」をつかもう
とするやり方は、確かに一理あります。
そして3つ目は、精神医療(お医者さん)が行っている分野です。
これは主に薬物療法ですが、気力体力が消耗しきって起き上がれな
いような状態の人を佳服させるのには、非常に役立つと思います。
以上の他にもあるかもしれませんが、大まかにとらえると以上の
ような対策をどの企業でも行ってきたのではないでしょうか。
しかしこれら3つのやり方だけでは、カバーしきれない分野がある
と弊社では考えています。それは何かと言うと、
「ストレスが発生する原因を科学的に解析し、再現性ある解決策を
持っているかどうか」という点です。
従来行われている3つのメンタル不調対策は、どれもストレスは
なぜ発生し、それをどうやれば止められるのか、ということについ
て科学的な検証をし、その上で解決策を持っているとは必ずしも言
えないのではないかと思います。
ストレスがメンタルヘルス不調を作りますが、ストレスとは一体
何なのか、とうことが明確にわからないと、対策も非常にあいまい
なものになってしまうのです。
従来、一般的に行われてきたメンタルヘルス不調予防対策として
のラインケア、セルフケア研修などでは、次のような内容のものが
多かったのではないでしょうか。
・うつはこころの風邪ですよ、と説明する。
・ストレスが溜まったら、運動しましょうね、と説明する。
・お互いの話を聴きましょうね、と説明する。
・明るく、前向きな考え方をしましょう、などと説明する。
・時には、朝日を浴びて散歩したり、お風呂に入ってのんびりしま
しょう、と説明する。
・趣味を持ちましょう、と言う。
・適度な飲酒は時にはいいですよ、と説明する。
これらの対策は確かに大事なのですが、ストレスと言うものがな
ぜ発生するのかという根本的な原因が、まだ科学的に研究されてい
ない時代の初歩的な「生活の心得」のようなものだと思います。
科学というものは、日々進歩発展します。特に2010年以降、脳科
学、心理神経免疫学、などの分野で様々な発見があり、現在では、
ストレスと言うものは、脳内の情動の発電装置と言われる「扁桃体」
という部位が、慢性的に興奮することから生み出される、というこ
とが、世界中の科学者たちの研究によりわかってきました。
「溜まったストレス」を吐き出すのに、お風呂に入ったり、朝日
の中を歩いたり、適度に飲酒したりするのはいいですが、それでは
根本対策とは言えず、またあまり科学的とは言えません。
ストレス対策を科学的に考えるとはどういうことでしょうか。
一例をあげます。扁桃体には「顔反応性細胞」という細胞があり
ますが、この顔反応性細胞は、相手の「表情」によって電気を発生
させ、興奮します。これが意味することとは、こういうことです。
メンタル不調に陥る人は、その人が毎日所属している職場や家庭
に、その人が苦手とする「表情」が存在しているということです。
これは特定のAさんの表情が苦手ということではなく、メンタル不
調になる人が苦手とする「一定の表情パターン」があるということ
です。
また扁桃体は、激しい声や激しい身振り手振り、などにも激しく
反応します。
以上のようなことが科学的にわかっているのですが、そうすると
予防対策として何をすべきかが見えてきます。
たとえば以下のようなことが一例です。
<セルフケア法の一例>
・どういう表情が苦手なのかを明確にし、その表情に扁桃体が興奮
しないように、セルフメンタルトレーニングスキルを身につける。
・扁桃体興奮は、ネガティブな感情を自分で解放できると鎮静化す
るので、その感情解放スキルを身につける。
・扁桃体興奮は、自分の要求(Demand),見通し(Predictability),支
援(Support)、の3つを自分でコントロールできると、鎮静化しや
すいので、このコントロールスキルを身につける。など。
<ラインケア法の一例>
・メンタルヘルス不調者は、その人にとっての「苦手な表情」に扁
桃体が慢性的に興奮してメンタルダウンを発生させるので、上司
自身がいつも穏やかな笑顔でいられるように、上司向けに自らの
ストレスコントロール法を教える。
・上司自身が、自分自身の上司の表情で扁桃体が興奮したり、また
メンタル不調者の表情を見ると扁桃体が興奮したりするので、上
司自身にメンタルトレーニングを行うか、またはセルフメンタル
トレーニングスキルを身につけさせる。
・扁桃体興奮は、自分の要求(Demand),見通し(Predictability),支
援(Support)、の3つを自分でコントロールできると、鎮静化しや
すいので、このコントロールスキルを身につけることで、上手な
部下指導法を民つけてもらう、など。
他にもいろいろありますが、とりあえずこのくらいにします。
メンタルヘルスの世界のもっと最先端の科学を!
今年は、こういう視点で皆様のお役にたつよう励みますのでよろし
くお願いいたします。
2014/01/05
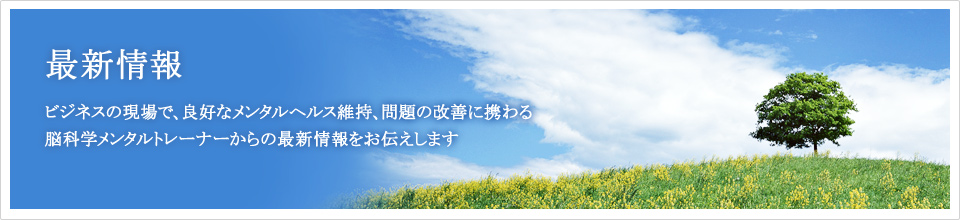
 前へ
前へ