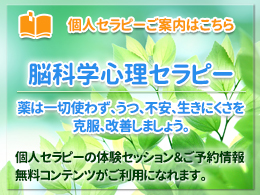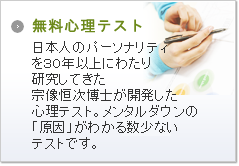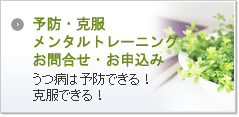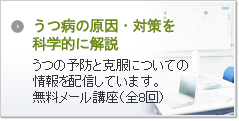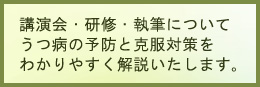科学で実証されたメンタル予防スキルを導入すれば、うつを防げる
多くの企業のメンタルご担当者様とお会いしていてきづいたことがあります。
それは、よくこんなことを言われている方が多かったのです。それは、・・・
「メンタルの予防策って、どれも同じなんですよね。他にないんですかね」と。
私は効果があれば同じでもよいのではないかと思いましたが、多くのご担当者様のおっしゃっていることはどうも違うところにあるように思いました。そしてお話をしているうちにわかったことがあったのです。どういうことかというと、
従来広まっているメンタル不調の予防対策は、「早起きして朝の光をあびましょうね」とか、「スポーツしましょうね」とか、「ストレスためないように時にはカラオケに行きましょうね」とか、「話を聴いてもらいましょうね」などのように、なんとなく、あらためていわれなくたって、わかりそうなこと、つまり「ノウハウ」ではなく、道徳の授業のようになっている、ということを言われているのではないかと思ったのです。
道徳の授業が悪いと言うのではなく、そこにわざわざ忙しい仕事の時間を割いて聴くには、ちょっとものたりないと感じるもの、または専門家の話にしては、ちょっと気を利かせれば誰でもがわかりそうな内容と思えるもの、ということなのではないかと思います。
でも、こういう予防対策セミナーを行っている企業は案外多いのではないでしょうか。ご担当者様から、同じようなお話をよく聴くので。
私は思ったのです。従来のような内容のセミナーはもちろん大事ではありますが、これからのメンタル予防セミナーは、もっと進化する必要があるのではないか、と。そしてそれは、「科学で実証された、再現性あるスキル」をお伝えしていくものになるべきだろうと思います。
たとえば、メンタル不調は、扁桃体興奮により引き起こされますが、扁桃体興奮は相手の「ネガティブな表情によって」引き起こされます。
これは科学的事実です。とすると、ネガティブな表情をした上司・部下が多い職場にメンタル不調者が多く発生することがわかります。ネガティブな表情とは?
例えば、イライラした顔、とげとげしい顔、険しい顔、不安が強い顔、無表情、能面顔、あきらめ顔、など。
こういった表情がメンタル不調者をたくさん生み出す組織になるのです。
こういった表情をたくさん生み出す組織とはどういう組織なのか、という説明は別の機会に譲ります。でもなんとなく想像がつくのではないかとおもいます。
では、笑顔の人がたくさんいる組織はメンタル不調者が少ないのですが、笑顔になる人をたくさん育てるにはどうしたらいいのでしょうか。
いろいろありますが、スキルとして身に着けやすいもののひとつとしては、科学的に実証された、ストレスマネジメントスキルを身に着けることがあると思います。
ストレスマネジメントの方法とは、大きく2つあります。
一つは、蓄積したストレスをどう解放するか、という方法。ストレスコーピングと言われるものは、これに入ると思います。歌を歌うとか、酒を飲むとか、マッサージを受けに行くとか、朝の光を浴びるとか、など。
これは確かいに大事ですが、たまったストレスをどう解放するか、ということなので、ストレスが蓄積することにそもそも対処をしていません。
二つ目の方法は、「自分の要求に見通しを付ける」という「見通し管理」という方法です。
ストレスとは、そもそも「見通しがつかないこと」が起きるときに発生します。
リストラされる、給料が下がる、やったことがない仕事先に配属させられる、知らない人間関係の中に入れられる、思い通りにならない上司・部下の中に配属させられる、いままでやったことのない売り上げ数字を求められる、など。
こういう見通しの立たない状況の中におかれると、私たちはストレスを感じるのです。この状況を上手にマネージする方法を知らないと、これは慢性ストレスになり、メンタル不調に陥ることになるのですね。
見通し管理の方法を自然と身に着けている人は必ずおり、そういう人は自動的に見通しを立てられるので、このストレスを「意欲」に変えて行けるのですが、見通しを立てる方法を知らない人は、このストレスを「苦しいもの」ととらえるようになり、過度の飲酒、過食、人間関係の悪化、などの方向に向かうようになり、メンタル不調に陥ります。
私たちの「心」は見えないものですが、我々の脳や免疫反応などは、一定の刺激に対して、非常に法則的に動くものであり、よって脳や免疫などの反応を研究すると、ストレスにどう対処すれば我々がメンタルダウンしないか、ということがわかるのですね。
科学に実証されたスキルとして学んでいく事ができるのです。
ストレス蓄積を解放するストレスマネジメント法だけでなく、見通し管理法というストレスマネジメント法を組織に導入されることをお勧めします。
2013/12/24
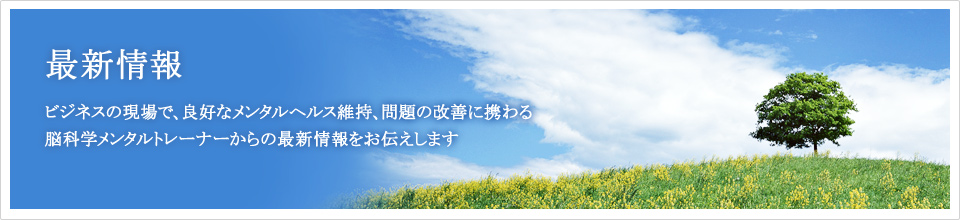
 前へ
前へ