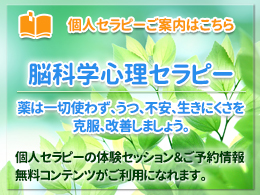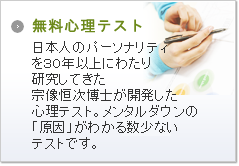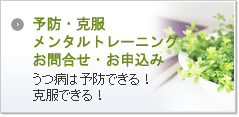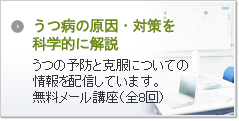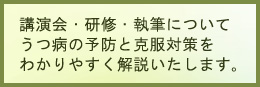企業メンタルご担当者様向け情報「健康経営の重要ポイントが見えると、うつ、メンタル不調も解決のヒントが見える」
ここ数年、健康経営、と言うキーワードが脚光を浴びていますね。東証では、健康経営銘柄、という企業を指定して健康経営に力を入れている企業がメディアに紹介されるなどしていますので、だんだん認知度が高まってきました。
もともと健康経営とは、弊社顧問の筑波大学名誉教授・宗像恒次博士が、1994年にロバート・ローゼンが執筆した「ヘルシー・カンパニー」という本を日本語に翻訳したあたりを草分けとして、以後、少しづつ認知が広まってきたように思います。
ちょうどそのあたりから、私も宗像博士の元で健康心理学び始めたのです。
その視点で言うと、私たちが考えている健康経営とは、昨今の健康経営とは少し違う視点がありますので、ご紹介したいと思います。
昨今の健康経営は、健康診断を早めに受診しましょう、と言うものが多いように感じます。でも、これだけだと、たぶん、企業はコスト増になってしまうだろうと私たちの立場からは考えます。
なぜか。結論を言うと、健康とは、病気がないこと、ではなく、病気があるなしにかかわらず、精神健康度が高い、生き方、働き方をしているかどうかを指すからです。
ご説明します。
もともと病気とは、健康心理学の定義では、「かかる病気」が多かったのです。たえば、伝染病とか、ウィルス性のものとか。これは、検査すればすぐわかりますから、薬を投与するなどして、対処法は明確でした。
しかし、昨今では「かかる病」より、「自ら作り出す病」が多いのです。これはストレス性のものがそうです。生活習慣病、がその代表例です。あと心因性のものものもそうですし、メンタル不調もそうです。
これらの病気は、検査しても原因が見つからないことが多いのです。それはそうです。ストレス性のものですから。かりに見つかったとしても、再発しやすいのです。
ストレスが原因で病になっていますから、症状を消しても、ストレスがたまりやすい生き方溜まりやすい生き方、働き方をしている限り、また症状は再発リスクがあるのです。
メンタル不調などはまさにその代表例でしょう。
これにしっかり対処するには、今ストレスがたまっているかどうか、と言うことではなく、ストレスがたまりやすい生き方、働き方をどう変えるか、と言うことなのです。
具体的に言うと、「周りに認められたい」という生き方・働き方をやめ、「たとえ周りに求められなくても、自分が満足できる生き方、働き方」に変換する、と言うことになります。
健康心理学では、前者の生き方・働き方を、他者報酬追求型人生(労働)、と言い、後者を自己報酬追求型人生(労働)、と言います。
今まで私たち日本人は、周りに認められたい、という強烈に強い欲求に突き動かされて、生き・働いてきたのです。高度成長期まではそれでよかtったです。
しかし現代では、認められたいと思っても、ポストが十分あるわけでもないし、賃金が必ずしも上昇するわけでもないし、リストラされるかも知れないし、要は「認められない」事が多いのです。
周りの評価をものすごく気にしたプロ野球・清原選手は、現役引退後、ものすごく太りましたね。メタボにもなった。認めてもらえないというところから来るストレスを癒すために、暴飲暴食に陥ったと私は推測します。メンタル不調にも陥ったでしょう。
一方、イチロー選手は、周りの評価を気にしているでしょうか。そもそも周りの評価は、自分ではコントロールできないものです。イチロー選手は、「コントロール出来ないものには、フォーカスしない」を貫いている人です。
イチローは、メタボにはなりませんね。
周りに認められたい、という欲求は日本人いものすごく強いパーソナリティですが、21世紀にもこれを持ち続けると、ストレスが原因の病(=自ら作り出す病)になっていくのです。この生き方・働き方を変えないままに、健康診断だけを早めに行っても、結局は病は再生産され続けることでしょう。
すると、結局は企業はなんどもなんどもコストを支払うことになり、無限のコスト増になるのではないでしょうか。
メンタル不調対策は、まさにこの状況に落ちいているのではないでしょうか。うつは何度も繰り返していますね。そして、結局は、繰り返す人を会社から追い出すことしか、対策はなくなってしまうのではないでしょうか。
実際、そういう企業は多いかもしれませんね。
話を戻すと、生き方・働き方を変える支援技術が必要なのだということです。
もともと弊社が行っている心理療法は、産業保健スタッフの方々に身に着けていただくための、行動変容支援の技術として開発されたものです。現在も、宗像博士指導の下、約1000人以上の産業保健スタッフがこれを学んでいるのです。
生き方・働き方を変える、支援をするものです。
そのことで、本人の慢性ストレスを解消し、結果としてメタボや生活習慣病や、その他、メンタル不調を含む、ストレス性の病を改善していくための支援技術なのです。
周りの評価を気にする生き方は、常に不安や怖れを根底に持っています。認められるだろうか、認めてもらえない。アップダウンの激しい生き方です。力にない人は、ずっと落ち込んだままになります。
これがメンタル不調です。
一方、周りに認められなくても自分で自分を認められる生き方・働き方は、自分が最低限評価できる、喜びのある生き方・働き方になるので、前者よりもストレスがたまらないのです。それどころか、自分の中に喜びのエネルギーを燃やし続けながら生き、働くことができるのです。
こういう視点で健康経営をとらえると、精神健康の高い生き方・働き方ができることがお分かりでしょう。これが本体の健康経営なのではないかな、と健康心理学では考えるのです。
自然とメンタル不調も改善されていくことがお分かりいただけると思います。
厚労省のメンタルへルスHP「こころの耳」では数ある心理療法の中で、唯一”メンタルヘルスカウンセリングを行うカウンセリング”と紹介しされているものです。
健康心理学に基づく個人カウンセリング、ラインケア、セルフケア教育、またはヘルスカウンセラー育成教育、に関心持っていただける方は、以下からお問い合わせください。
既存のメンタル対策と組み合わせ、某上場企業では3年半、初回うつ休職者の再発0%の結果に貢献しました。
詳しく知りたい方は、下記お問合せフォームから資料請求をどうぞ。
2016/08/03
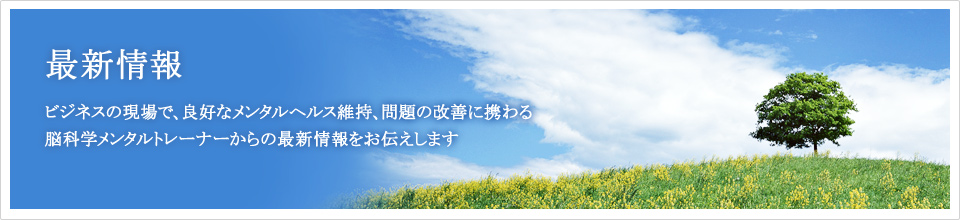
 前へ
前へ