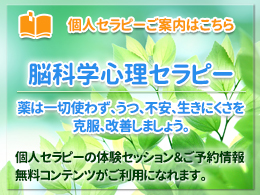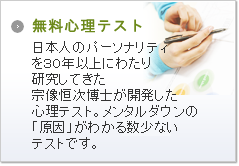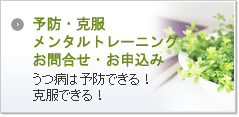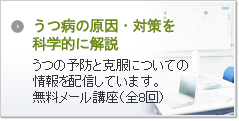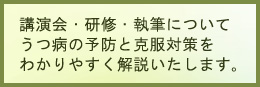企業メンタルご担当者様向け情報「扁桃体を鎮めれば自律神経はチューニングされ、慢性ストレスが改善される」
最近、ウェアラブルという自律神経を測定することでストレスを測定する機器がいろいろ発売され、注目を集めていますね。
若者向け雑誌「TARZAN(ターザン)7月14日号」は、1冊丸ごと”自律神経チューニング術”というと言う特集を組んで、自律神経を調整することで、様々なストレスに対処する方法が特集されていました。
たまたま私はターザンを読んでいた時に、同時に「月間脳神経科学2014年6月号」も読んでいました。このP618には、和歌山県立医科大学準教授・上山 敬司氏の「扁桃体と自律神経」という論文が載っていたのです。
これによると、こう書かれています。「扁桃体は機能的に大脳辺縁系に分類され、情動に関係する。情動とは情と動の合成であり、心身の動揺を伴う感情の変化である。情動には、自律神経活動の変化、たとえば血圧や脈拍、消化管運動、発汗などの変化を伴う」
つまり、端的に言うと、扁桃体が自律神経活動をコントロールしている、と言うことです。ここまでわかれば、では自律神経を安定させるには、対処法としては扁桃体を安定化させればよいのだ、と言うことはわかるでしょう。
自律神経が不安定になると、それこそいろいろな症状が出ますね。睡眠がうまく取れなくなったり、食欲がわかなくなったり、お医者さんの方が詳しいと思います。
で、ターザンを見ると偏桃体の話は出てこないのですね。代わりに様々なストレスコーピング法が出てきます。
元気な声でおはよう、と言おう、とか、スケジュールを確認しよう、とか、朝刊をきちんと読もう、とか、暑いシャワーを浴びよう、とか、朝の光を浴びよう、とか。
どれも大事なのですが、扁桃体そのものにダイレクトの働きかけて情動を安定化させよう、という手法がない、ですね。
ここがメンタルの世界の不思議なところです。
論文で、扁桃体が自律神経に影響を与えている、とわかっているのに、扁桃体そのものに働きかけて安定化させよう、という根源的な手法が紹介されていない。これまでの心理学も、考え方を変えようとか、前頭葉に働きかけるものはありますが、扁桃体そのものに働きかけるものがないですね。
扁桃体が興奮しすぎると、前頭葉が機能しなくなるので、考え方を変えようとするのは難しいのではないかと思います。
まあ、でも、私たちがやっているような扁桃体にダイレクトの働きかける手法が、ほとんどメディアに出てこない問うことは、ある意味、希少価値があるということかもしれません。
結局は、サービスを受ける側が、いつかそういう方法はないのか、と気づく日が来るのではないかな、と思うからです。それを信じて室力を磨いていこう! と思います(^^)
厚労省のメンタルへルスHP「こころの耳」では数ある心理療法の中で、唯一”メンタルヘルスカウンセリングを行うカウンセリング”と紹介しされているものです。個人カウンセリング、ラインケア、セルフケア教育、またはヘルスカウンセラー育成教育、に関心持っていただける方は、以下からお問い合わせください。
既存のメンタル対策と組み合わせ、某上場企業では3年半、初回うつ休職者の再発0%の結果に貢献しました。
2016/07/09
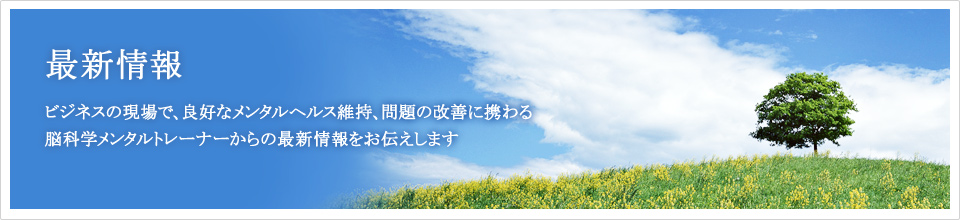
 前へ
前へ